このブログを検索
神戸・芦屋で毎月開催!ゲシュタルト療法を体験できるオープンワークショップ「ゆるゲシュ」。対話を通じたグループカウンセリングで、人間関係の悩みや自己成長のヒントを得ませんか? 「キレる私をやめたい」人、心理学に興味がある方、カウンセリングを受けたい方にもおすすめです。初心者歓迎、学びと気づきの場へぜひご参加ください!
注目
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
「ゲシュタルト」とは–ゲシュタルト療法のキーワード
Gestaltとはドイツ語で、英語にも日本語にも、直接ぴったりくる訳語が見つからない言葉です。
pattern, form, shape, configurationといった英語が近いニュアンスの言葉のようでうが、もっといろんな意味が含まれています。
日本語では、「形態・姿」「まとまりをもった全体性」といった意味となりますが、「ゲシュタルト」(あるいは「ゲシタルト」)とカタカナで書かれることが一般的です。
ゲシュタルトセラピーの源流のひとつに「ゲシュタルト心理学」があります(その他のルーツは、精神分析や現象学、実存主義哲学、仏教などです)。
ゲシュタルト心理学では、ヒト(や生き物)は、周りの環境の刺激を、ひとつの全体像としてまとめて捉える傾向を扱います。
ゲシュタルトの原則
20世紀初頭、マックス・ヴェルトハイマー(Max Wertheimer)らは、「ゲシュタルトの原則 Gestalt principles(Gestalt laws)」として次のような法則を挙げました。ヒトは、近いものや似ているものをグループとしてまとめたり、閉じた図形を見る傾向があるということです。
1.近接の法則(Law of Proximity)
距離が近いものは、同じグループとしてまとまって認識されやすいという法則です。
次の図を見ると、左側の8つの円がひとまとまりのグループとして認識されます。右側の8つも同様ですね。
2.類同の法則(Law of Similarity)
3.連続の法則(Law of Continuity)
4.閉合の法則(Law of Closure)
5.共通運命の法則(Law of Common Fate)
他にも、図と地(Figure & Ground)など、いくつもの「ゲシュタルトの法則」が発見されています。
ゲシュタルト心理学者たちが研究したのは、主に視覚的体験についてですが、同じような「法則」は、ヒトや生き物の「体験」にもあると考えられます。
体験のゲシュタルト・サイクル(気づきのサイクル)
 |
| Dave Mann”Gestalt Therapy 100 Key Points and Techniques” |
ゲシュタルト療法では、私たち人間や生き物の体験もまた「ゲシュタルト」を持っていると考えています。
お腹が空いていたら食べ物に目が向くし、喉が乾いてたら水を探します。
お腹いっぱい食べることができたら、食べ物への注目はなくなり、代わりに違う欲求が図として表面に浮かび上がってきます。
こうした欲求とその充足のあり方は「体験のゲシュタルト・サイクル」あるいは「気づきのサイクル」と呼ばれます。
体験のゲシュタルト・サイクルには、次のようなステージがあります。
(1)感覚 sensation
(2)気づき awareness
(3)可動化 mobilization
(4)行動 action
(5)接触 final contact
(6)充足 satisfaction
(7)引きこもり withdrawal
たとえば職場で上司からひどく叱責されたとします。本当は私の失敗ではないので、上司の叱責は見当違いなのですが、なかなか上司に反論するのって難しいですよね。
そういうとき、お腹に「ムカムカ」する感覚があるとします(感覚)。
そのムカムカを感じていると、「この上司に腹が立っている」という気持ちに気づくでしょう(気づき)。
両腕にギュッと力が入り、何か言いたいことがお腹から登ってきます(可動化)。
「お言葉ですが、それは私の失敗ではありません! よくこの文書を読んでください!」といいながら、机にバンと資料を置きます(行動)。
上司も「なんだその態度は!」と言い返してきますが、何度かぶつかってお互い言いたいことを主張します(接触)。
少し口論にはなりましたが、主張を伝え合ることができたので、気持ちはすっきりしました(充足)。
仕事が終わると、先ほどのことは忘れておいしくビールを呑みます(引きこもり)。
こんな例を考えてみましたが、でも上司に対して言い返すなんて、実際はなかなかできないですよねえ。「長いものには巻かれろ」で、(本当は自分の失敗ではないのに)と思いつつも、飲み込むことも多いのではないでしょうか・
未完了の体験(ゲシュタルト)
呑み込んでしまうと、「言えなかったこと」「できなかったこと」「獲得できなかったもの」が、「未完了の体験(ゲシュタルト)」として残ります。
これは、ストレスや欲求不満の体験にもなりますし、強い未完了はトラウマ的な体験ともなります。
こうした「未完了の体験」が、心の多くを占めるようになると、人はそのことで苦しんだり、自分自身の人生を生き生きと生きることが難しくなります。
ゲシュタルト療法のワークでは、こうした「未完了の体験」に注意を向けて、ワークの中で未完了を完了させていく、といった試みをすることがあります。
「本当はあの上司に無茶苦茶腹が立っていて、この分からず屋!って言ってやりたかったんです」
と気づいたら、ゲシュタルト療法のファシリテーターは、「ではその椅子に上司が座っていると思って、感じた通り言ってみてください」と提案するかもしれません。
クライエントが空の椅子(あるいは座布団)に、十分自分の気持ちに触れながらそう伝えてみると、上司に対する未完了が収まることもあります。
最初に挙げた例みたいに、上司と口論することは難しくても、もっと上手な伝え方が分かることもあるでしょう。
あるいは、上司とのことが完了したら、今度は「この分からず屋!って言いたかったのは、実は父親に対してだったと思う」と、父親との葛藤が図として浮かび上がってくることもあります。
こんなふうにして、ゲシュタルト療法のワークは進んでいきます。
---
第4回ゲシュタルトセラピー@大阪天正寺
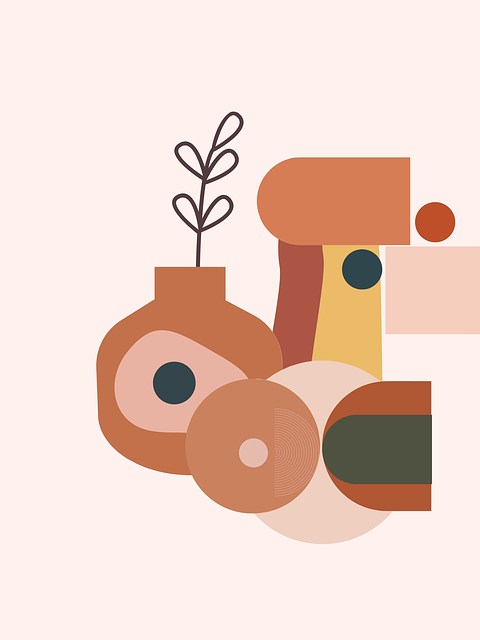







コメント
コメントを投稿